
メルボルン中央駅
2025年2月20日(木)から24日(月)にかけてAsia TOPAの視察でオーストラリア・メルボルンに滞在した。Asia TOPA(アジア太平洋舞台芸術トリエンナーレ Asia-Pacific Triennial of Performing Arts)は2017年から3年に1度メルボルンで開催されている芸術祭で、今回はコロナ禍の影響で2020年以来5年ぶり3回目の開催。3週間弱の会期中に62ものプログラム(うちperformanceカテゴリーは36)が並ぶ大規模な芸術祭である。

アーツセンターメルボルン・ハマーホールのバーカウンター
今回の視察は「国際展開を目指す舞台芸術の担い手の育成事業」であるIN TRANSITの事業の一環として実施されたものであり、このレポートはその成果報告として書かれている。しかし視察レポートの本編に入る前にまずは「国際展開を目指す舞台芸術の担い手の育成事業」で批評家が育成対象となっていることの意味について考えておきたい。
舞台芸術の担い手としての批評家の国際展開とは、そのための育成とは一体何を意味するのだろうか。IN TRANSITではアーティストと技術スタッフ(舞台監督)、そして批評家が「国際展開を目指す舞台芸術の担い手」として育成対象になっている。海外で作品を創作・上演し、あるいは海外のアーティストとのコラボレーションを行なうこと。海外での創作・上演に携わること。その意義の問い直しの可能性こそあれ(なぜ国際展開をするのか?)、アーティストや技術スタッフの国際展開の意味するところは明確だろう。実際、アーティストと技術スタッフの育成プログラムは、海外で創作・上演を実現するための知見の蓄積とネットワークの獲得を目的としたものを中心に組まれている。では批評家はどうか。
そもそも「批評家の国際展開」と言われて具体的なイメージが思い浮かばないのは、アーティストやスタッフと同じようなかたちでの国際展開が批評家においては行なわれていないという事実も大きいだろう。そしてこの状況はおそらく、ローカルな批評家こそがローカルなアーティストの取り組みをより理解できる(ことが圧倒的に多い)という端的な事実に基づいている。いや、たとえば『ポストドラマ演劇』のハンス=ティース・レーマンのようにその著書が国際的に参照されている例はもちろんあるのだが、それらはどちらかというと研究の領域の話であるだろう(そして言うまでもないことだが、多くの演劇研究者は大なり小なり国際的なネットワークのなかでその研究活動をしている)。
あるいは、東南アジア圏のパフォーミングアーツに関する言説を発信しているArtsEquatorのような組織の活動に目を向けるべきだろうか。私の書いた批評がArtsEquatorに掲載されるようになれば、なるほどそれはある種の国際展開と言えるかもしれない。しかし、圏内での行き来が比較的容易な東南アジア圏の批評家がArtsEquatorのようなプラットフォームに参加するのと、日本の批評家である私がそうするのとでは、自ずとその意味合いは変わってくる。国際的な発信をする以前に、日本の舞台芸術批評は惨憺たる状況にあるという(少なくとも私からはそう見える)厳しい現実もある(アーティストの実践に対して批評の絶対数が圧倒的に足りていないことや批評への対価が概して安過ぎることなど問題は山積みである)。いずれにせよ、「批評家の国際展開」は自明のゴールとしてではなく、プログラムを通じて問われる前提として向き合うべきものだろう。
さて、これまでのところ、IN TRANSITにおいて批評家を対象に実施されているプログラムは①育成対象アーティストの作品の②劇評執筆と海外の舞台芸術フェスティバルの視察の二つである(加えて今後は座学も予定されている)。これらは「批評家の国際展開」をどのように実現し得るのだろうか。

アーツセンターメルボルン外観
①育成対象アーティストの作品の劇評執筆に関してはなるほど、たしかにそのようなかたちで批評家が「舞台芸術の担い手の国際展開」に資することは十分にあるだろう。日本の舞台芸術が、ことにその先鋭的な実践が国際的に展開していくために、国内のコンテクストの海外への発信と国内における知見や思考の蓄積が、つまりは舞台芸術をめぐる言説の活性化が重要であることは間違いない。その意味で、IN TRANSITというプログラムがアーティストや作品の国際展開を目指すにあたって、それらをめぐる言説を合わせて発信していくことには十分な理由がある。
だが、批評家の側からすればどうか。このように一定の期間をアーティストに伴走するかたちで継続的に劇評を出していくことにはもちろん一定の意義がある。しかし劇評執筆は結局のところ私にとっては「通常業務」の範疇である。そこに育成プログラムとしての特段の意義を見出すことは難しい(もちろん、今後の座学を踏まえることで、あるいは執筆の条件や媒体などによってはそこに育成プログラムとしての意義が生まれてくることもあろうが、少なくとも現時点ではそのような組み立てになっているわけではない)。
では、②海外の舞台芸術フェスティバルの視察についてはどうだろうか。私のようなフリーの演劇批評家にとって、海外視察は主に費用の面でかなりハードルが高いものであると言わざるを得ない。大学に所属する研究者のように研究費から出張費を捻出できるわけでもなく、そもそも劇評の原稿料は残念ながら海外視察の費用を捻出できるほどの水準にはないからだ。さらに、これまでにも何度か指摘してきたことだが、日本の舞台芸術界において、批評家は公的な助成の対象となることがほとんどない。個人では実現が難しい海外視察を可能にし、新たな知見を獲得する機会を提供しているという点において、②海外の舞台芸術フェスティバルの視察は批評家の育成プログラムとして十分な意義を有していると言えるだろう。

Asia TOPAグッズ
では、そこで得られる新たな知見とは具体的にはどのようなものか。日本ではまだ紹介されていないアーティストや作品に触れられることが重要なのは言うまでもない。しかし、加えて重要なのは、フェスティバルにラインナップされたアーティストや作品をある程度まとめて観ることで、その背後にあるコンテクストにも触れることができるという点だろう。ここでいうコンテクストにはフェスティバルの性格や現地の舞台芸術を取り巻く環境はもちろん、そのさらに背後にある社会的状況なども含まれている。ある場所でどのようなアーティストが活動しどのような作品が上演されるかは、そこがどのような場所であるかと不可分なかたちで結びついているのだ。
私が近年特に関心を寄せるLGBTQを例に挙げれば、同性愛が法的に禁じられている国では、同性愛者がアーティストとして公に活動することも、同性愛についての作品を公に上演することも難しいだろう。一方、同性婚が法制化されている国ではそれを前提とした作品がつくられ上演されることになる。あるいは、メルボルンの街中では見るからにクィアな人々とごく普通にすれ違うということ。ある国や地域で同性愛が法的に禁止されているか、同性婚が法制化されているかは調べればすぐに分かることだが、現地で体験しなければわからない街の空気や物理的な条件といったものもたしかにあるのだ。
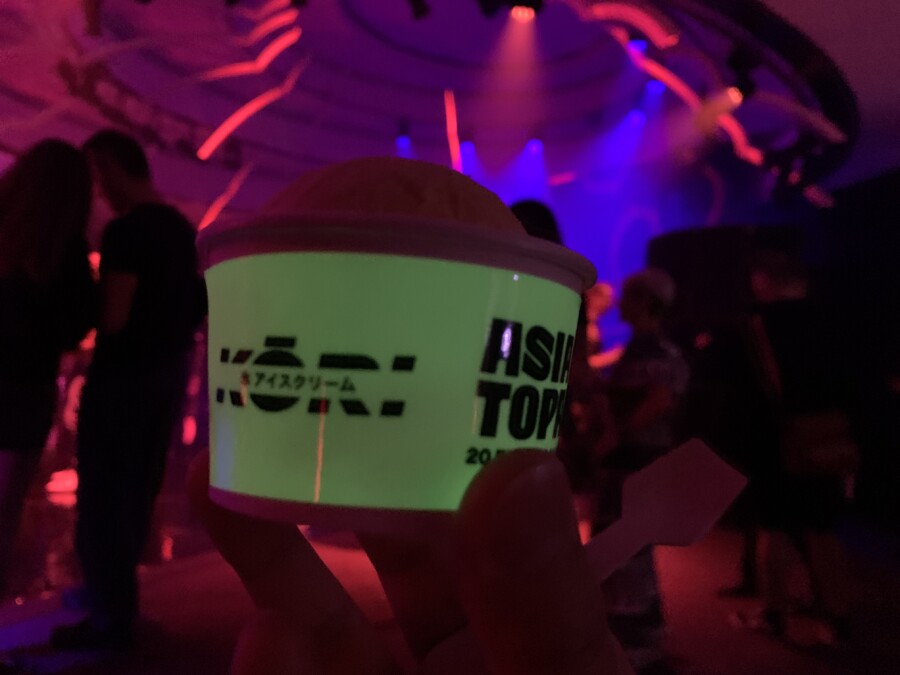
club 8にて
まだ見ぬアーティストや作品、日本とは異なるコンテクストに触れ、新たな知見を獲得すること。それらの紹介を通じて日本の舞台芸術を相対化し、あるいは今あるそれらとはまた別の可能性を示すこと。いわゆる国際展開という言葉からイメージするものとはズレもあろうが、IN TRANSITにおける批評家の育成プログラムの意義を、あるいは批評家の国際展開ということの意味を、私はひとまずこのように考えている。
執筆:山﨑健太
