2024年にスタートした、舞台芸術の担い手を対象にした育成事業「IN TRANSITー異なる文化を横断する舞台芸術プロジェクトー」の初年度成果報告会が2025年3月28日に開催されました。前半の、育成対象者による今年度の成果や課題、今後についての発表の後は、事前に育成対象者から集めていたトピックを元に、会場にいる来場者も交えながらオープンディスカッションを行いました。
国際展開の新しい価値をどう言語化し共有するか
後半の司会進行は、precogの黄木。「この事業の枠組みは、海外展開を前提としています。先ほど、日中当代表演交流会の萩原さんからも、そもそも国際的であることの意味は何か、誰が価値づけるのかという問いかけがありました。坂本さんからも、海外展開の価値をどう言語化し、どうほかの人に還元していくのかということを質問としていただいています。まずは、その辺りの話から始めてみたいと思います。」とディスカッションをスタートしました。

IN TRANSITの主催・企画運営を行うprecogの黄木
まず萩原雄太さんから、日中当代表演交流会が、公演を最終成果物に定めていない理由として、目的に向かって突き進むことや、目的に対して集められることに対して、違和感を持っているからとした上で、次のように語ります。「そうではない形で何ができるか考えたときに、公演をするというよりも、“新しい価値観”をつくることなのかと思っています。その際に、我々だけではできない、他の文化の背景を持った人と一緒につくっていくのは、すごく意義があると思っています。」
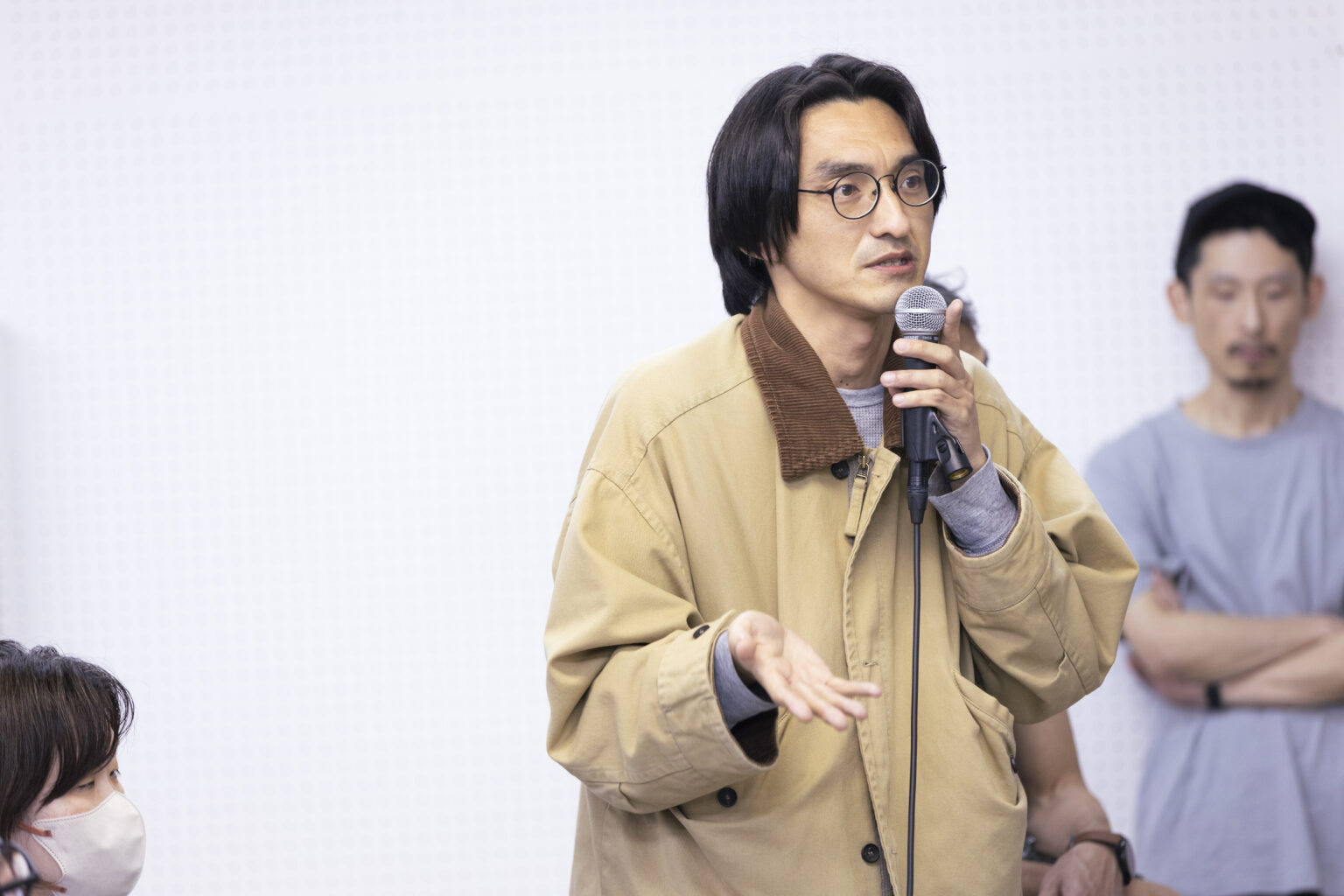
日中当代表演交流会メンバーの萩原雄太さん
続いて坂本ももさんからは、「とはいえ、私たち範宙遊泳は十年ぐらい前からずっと海外公演や国際共同製作をしてきて、作品作りを前提にしてきました。それとは何が違うのかみたいなことが、いまいちまだしっくりきていないんです。海外展開や作品をつくることに、価値があるとも思っているし、でも同時に新しい価値についても考えていかねば、という感覚がある。その辺、皆さんはどう考えていますか?」と、他の参加者に質問が投げかけられました。
批評だけでなく、自身も作品づくりに関わっている山﨑健太さんは、「僕はまだ自分の作品を海外に持っていったことはないのですが。一方で、先ほども話しましたが、僕が特に関心を持っているジェンダー、セクシュアリティ、LGBTQに関しては、日本とほかの国では文脈や置かれている状況が全然違います。作品を見たり、その作品が上演されている状況を知るということ自体が、新しい価値を創造したり、日本にない世界を見出すことができるわけです。そのこと自体は、ほかのトピックでも同じことが言えるんじゃないかと思います」と、海外に行くことの意義や新しい価値の創造について感想を述べました。

舞台制作者・プロデューサーの加藤奈紬さん(左)と批評家の山﨑健太さん(右)
続いて、来場していたBeri Juraicさんを萩原さんが紹介。Juraicさんは、イギリスのランカスター大学で演劇学の博士課程に在籍する研究者で、日英の演劇研究者・アーティストが交流するプログラム「Japan-Britain Contemporary Theatre Exchange」を開催しており、萩原さんはそこで2023年にワークショップを行っています。
Juraicさんは、こうした国際交流プログラムで何が生まれるのか、最初はわからなかったとした上で、萩原さんたちと色々な話をすることを通して、“一緒に時間を過ごすこと”が大事だと思った、と述べます。また、東浩紀さんの著書『観光客の哲学』にも触れつつ、これからは大きな劇場でたくさんの観客に向けた公演を行うことよりも、一人の観客に小さな影響があることや、アーティスト同士のエクスチェンジが重要だと思っていることなどを語りました。

ランカスター大学で演劇学の博士課程に在籍する研究者のBeri Juraicさん
続いて、別のトピックへ。黄木より「オル太のお2人、特にJang-Chiさんは今、別のプロジェクトで国際共同製作にも参加されていると伺っています。その中で、違う文脈の人たちと触れながら創作を行っていると思うのですが、どういうモチベーションで、どういう刺激をもらって活動されているのか、お伺いしたいです」と投げかけます。
Jang-Chiさんは、2024年から始まった、台北アーツフェスティバルのリサーチプログラムCruisingとKYOTO EXPERIMENTの共同製作として行われている企画に、日本、フィリピン、台湾の4人のアーティストで参加しています。
「この4者は、詩人・小説家、俳優など、それぞれスタンスや使っているメディアが違い、演劇と美術を横断するような活動をしている人が多い中で、メディアや形式自体をそもそも捉え直すことに意義があるなと思っています。また、言語が異なるので、通訳が行き交う中で話をしているのですが、翻訳による勘違いもあるし、そこにそれを介する意味が生まれると思っています。その“摩擦”みたいなものが価値であって、文化が移動してつくられる価値基準をもとに、国際共同製作であるかどうかは別として、自分は制作してると思っています」と、Jang-Chiさん。

オル太のメンバーのJang-Chiさん
同じくオル太のメンバーとして活動するメグ忍者さんからは、2013年に韓国のレジデンスプログラムにオル太が参加した際に、初めて演劇フェスティバルに出たこと、それ以来韓国との共同製作を続けていること、コラボレーションした韓国の演劇ユニットは解散してしまったけれど、個人的な関係はずっと続いていることを紹介します。「そういう、交流の蓄積が大事になってきています。適当な韓国語、日本語、英語で話しているんですけど、一緒にいた時間が長いと、お互い何を考えてるかわかるようになって。コミュニケーションが別の次元のコミュニケーションになっていってるような感じですね」と語ります。
同じく2013年からイタリアで共同製作を継続してきたマームとジプシーの林香菜さんは、「メグ忍者さんが言ってたこと、とてもわかります。やはり時間の蓄積が重要だったなと思います」と応じます。「マームとジプシーの場合は、藤田が戯曲を上げてから、その場で口伝で俳優にセリフを与えていく方法を取っています。イタリア人と一緒に製作した時は、稽古の場で生まれた藤田のセリフを、通訳者が英語に訳して、それを俳優が解釈してその場でイタリア語のセリフに固めていくという方法をとりました。結果的には、作品の理解度が上がり、作品に対するそれぞれの解釈が生まれました。そして、チーム力も上がり、本当の劇団みたいになっていったという経緯があります。」

マームとジプシーの制作と法人の代表を務める林香菜さん
続いて、前半のプレゼンテーションで、今回の国際共同製作でチューニングがうまくいかなかったと述べていた、筒井潤さんより。
「私は、国際共同製作に向いてないっていうことを実感しました。自分は、本当はゆっくり考え込む方なんです。ドイツの現場で相手役の方は、思ったことは全部言うタイプだったんですよね。それに対して私は慎重に、それまでリハーサルで何を積み上げてきたかとかを考え込んでしまう。そしたら、何か喋れよって言われてしまう(笑)。国際的に交流を重ねていくというとき、それは非常にコミュニケーション能力の高い人たちが潤う場になるという可能性はあると感じています。」

公演芸術集団dracomリーダーの筒井潤さん
筒井さんのコメントに対して、先日のバンコク滞在で本質的な問題と対峙していたと語った山本さんは、「コミュニケーションスキル能力が高くないと、というのは本当にそう思います。僕はそのスキルが高くないから、事故ったみたいな気持ちになることがたくさんあったんです。でも結局僕の場合は、鍛えていこうという方にシフトしていきました」と応答します。
そして、山本卓卓さんがかねてから考えていた、劇団員が友人なのか仕事仲間なのかという問題について触れながら、国際共同製作で一緒にやることになった人たちと何かを始める際に、友達になるきっかけを探していくようなものではないか、と語ります。
「お互いの親密になれそうな部分、信頼できそうな部分を探っていく過程は、言語という壁があってもなくても、基本的に人と人が出会って何かをやる際には同じだと思っています。そして、それには技術がいると思っているんです。それは、誰も教えてくれないテクニックです。何度かめげそうになって、それでもやってきた中で、人と何か一緒につくっていくとか、人と話ができるようになっていく、人と人がつながっていくための技術が、一つの財産だと思えるようになってきたんです。」

日中当代表演交流会メンバーの山本卓卓さん
範宙遊泳のプロデューサーとして、そして新しいプロジェクトのメンバーとして活動をともにしている坂本さんは、「コミュニケーションが上手じゃないからこそ、作品があったんじゃないかと思います。範宙遊泳のコラボレーションは、お互いの興味関心を出し合って戯曲を共同執筆して、演出も共同で行い、俳優も両国から参加するスタイルでした。作品を媒介にコミュニケーションを取る、ということをやってきたんだと思います」と述べます。
そして、日本でクリエイションするのと国際共同製作での行為自体はあまり変わらない気がするけれど、自分たちがやっていることの価値を、どうお客さんや関係者に届けていくか、そして、自分たち以外に還元することに難しさを感じていると加え、「これだけ色々なチームがあるこの育成プログラムを通して、何か見えてくるんじゃないかという気がしてます」と締めくくりました。

日中当代表演交流会メンバーの坂本ももさん
以上で、報告会のレポートを終わります。
2024年度からスタートしたIN TRANSITの1年間(活動自体は秋から始まったので実質は半年間)を、外部からの参加者の方も交えて、振り返る時間になりました。アーティストだけでなく、プロデューサーや批評家なども対象にした海外活動支援プロジェクトはこれまでにない新しい試みですが、現代における国際展開の価値や意味、そして、こうした育成事業の中で得られたものをどう言語化してひらいていくか、という課題を改めて認識する機会となりました。
今後も活動のプロセスを公開していく予定です。引き続き、Webサイトなどで活動を追っていただけると嬉しいです。

写真:前澤秀登
執筆:岩中可南子
舞台芸術の担い手の国際展開を支援するプロジェクト1年目の活動報告。「IN TRANSIT 令和6年度成果報告会」開催レポート【前編】
